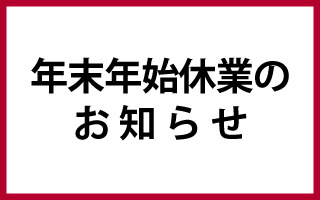【歌舞伎よもやま話】第七話「幕間」 / 語り:大城戸建雄
こんにちは。手ぬぐい専門店 麻布十番麻の葉です。
歌舞伎にまつわるよもやま話をお届けします。語りは大城戸建雄氏。麻の葉の歌舞伎手ぬぐいの原画を手掛け、歌舞伎に精通している大城戸氏による『歌舞伎よもやま話』をご堪能ください。
歌舞伎よもやま話「幕間」
「まくま」とか「まくあい」とか、人によって読み方が定まらないが、正しくは「まくあい」という、と古老からは聞かされている。つまり芝居がひと幕終わり、次の幕までの間の事で、舞台の奥では次の舞台の準備に忙しい修羅場となっていて、大道具小道具の黒子が秒刻みで動いている。
一方観客にとっては、トイレに行ったり、食事をしたり、劇場内を散策する、つまり休憩時間だ。
かつてこの幕間は、観客が自分の時間として、贔屓の役者が出ないときは芝居茶屋に戻って食事をしたり酒を飲んだり贔屓の役者を呼んで歓談したり、自分の幕間を作っていた。劇場としては、暗転として次の舞台装置準備のための時間で、江戸ではその時間を告知したようだが、上方では準備ができ次第と言う事で告知せず、拍子木が入ると舞台が始まる予告となったようである。
現代は、食事の時間なども決められて、だいたい25分か30分で幕間を劇場が仕切る。そして時間が来ると、大きなビニール袋を持って弁当箱やゴミの回収にやってくる。
これはこれである意味合理的ではあるし、劇場側にとっては時間調整がスムーズに運ぶメリットがあるようで、現代の若いひと達にはそれなりの受け入れ態勢が整っているようだ。さらに舞台の暗転が非常に効率よく行なわれるようになったことも事実である。しかし、効率を良くするのは観客、役者、劇場、いったい誰の為だろうか。
劇場に足を運ぶという事は、日常を忘れるための芝居通いである。祝祭空間という異次元での楽しみを味わうという事で、決して安くはない観劇料金を支払っている。幕間にその観客の余裕を演出できる時間がなかったら寂しい限りだ。劇場は、観客が、ゆったりした自己時間と自己趣味空間を確保することを保証するべきだと思う。しかし今の劇場のシステムは、観客の自由裁量時間を奪うという理不尽さが感じられるのである。
私が歌舞伎初体験の昭和30~40年の時代は、幕間もゆったりしたもので、取り敢えず緞帳が上がり、定式幕になって拍子木が入ったら(だいたい5分前)それまではロビーや劇場内で時間をつぶしていた観客はアナウンスが無くても自然に席に着いたものだった。
大阪道頓堀の中座、京都の南座には当時劇場内に、落語に出てくるようなお人好し夫婦が接客するおでん屋があった。幕間のたんびに、おでん1~2種類と燗酒1本を頼み、同席の芝居好きの先輩たちから芝居や役者の情報を収集するのが楽しみであった。そこで初心者は芝居の見所や役の知識を得たものだった。ごく普通のおじさんが常連で、結構大した見巧者であり評論家だったのである。それゆえ、民衆が育ててきた芸能文化という空気が、劇場という空間全体に漂っていたのである。そんな豊かな時間を味わえる空間=劇場がこの国においては再生されるのを期待したい。

歌舞伎座売店では、「麻の葉」の手ぬぐいを販売しております。「幕間」にはぜひお立ち寄りくださいませ。